
おはようございます。本日のお日柄は以下の通りです。
日出 4:42 / 64度
日没 18:53 / 296度
昼時 14:11
月出 2:22 / 55度
月没 17:56 / 304
正午月齢 27.7
みづのと み :(癸巳)前場安く、後場高し
仏縁 : 開店、移転など、新規に事を起こすことはもちろん、陰陽道で何事をするのも忌むべき日とされています。
ひらく : 拓 神使天険を開通する意の日で、建築、移転、開店、婚礼、などすべてに吉です。ただし葬式などの不浄時は凶です。
軫(しん) : 地鎮祭、棟上げ、落成式、神仏祭祀、祝い事よろず吉。
七赤 : 【天 象】秋・西風・天侯変り易い・雨・暴風雨・日没・涼気・夕ぐれ・新月・九月(酉月)午後五時~午後七時(酉刻)・西方三〇度【色 数】白色・四・九【象 意】悦ぶ・安楽・沢・金銭・酒食・愛嬢・色情・祝賀・結婚式・口論・雄弁・金融・不足・不充分・借金・経済・趣味・娯楽・御馳走・浪費・解逅の悦び・接吻・婚態・有終の美・浄土・清貧・遊興中・食事中・節度・恋愛【人 物】少女・芸人・芸者・ホステス・後妻・妾・出戻り女・金融業者・弁護士・親なし子。不良少女・飲食業者・通訳者・仲介者・歯医者【植 物】秋の草花類ー尾花・桔梗・月見草・しょうが・からし菜
天一天上 : 癸巳(みずのとみ)から戊申(つちのえ さる)までの16日間は天上に帰るため、この期間は天一神の祟りはなくなる。この期間を天一天上(てんいちてんじょう)という。天一天上の期間は天一神の祟りはないが、その代わりに日遊神が地上に降りて家の中に留まるため、この期間は家の中を清潔にしなければ日遊神の祟りがあるとされている。その年の最初の天一天上の1日目を「天一太郎」といい、上吉日とされている。この日に雨が降るとその後の天候が良くなくなるとされ、この日の天候によってその年の豊作と凶作を占った。
ぢう日 : 巳の日と亥の日が指定日で吉事を行えば吉事が重なり、凶事なら凶事が重なる日。婚礼や葬式にはよくない日とされています。
母倉 : 天が万物をあわれむこと、母が子をおもうような日。天が万物を育成する意味を持ち、とくに譜請、開業、婚礼などに吉日とされます。ただし二月の亥の日は重日と重なるので、仏事は避けた方がよいとしています。
東京のお天気 : 晴れ時々曇り
最高気温 35度 / 最低気温 27度
満潮 2:31 17:15
干潮 9:48 22:26
◇◇◇今日のひと言◇◇◇
今日は「拓」の日。名前の通り、心や考えに新しい風を通すのにぴったりです。何か始めたいと思っていたことがあれば、小さな一歩を踏み出してみましょう。「仏滅」だからこそ、余計な執着を手放す良いタイミングともいえます。また、「軫」の宿は学びや知恵にご縁がある日。静かな時間に読書や思索にふけるのも◎。月は有明の月(27.7)となり、まもなく新たなサイクルへ。運気を司る「七赤金星」は、素直な気持ちで人と接することで思わぬ良縁を運んでくれるでしょう。静けさのなかに、希望の芽がそっと顔を出す日です。
☆彡 ☆彡お花の事☆彡 ☆彡
ベンガルヤハズカズラ(花言葉「愛情」)キツネノマゴ科ツンベルギア属
インドのベンガル地方に分布するキツネノマゴ科ツンベルギア属のつる性常緑多年草です。葉はハート型で長さ15~20㎝、幅10~15㎝、細かい毛が密生し縁にはギザギザがあります。つるは長く伸びて木質化します。花茎は葉腋から出て房状に8~10個の花が垂れ下がり、直径5~8㎝ほどの淡い青紫色の花を次々と咲かせます。花筒部は釣り鐘形、花びらの部分は5つに分かれます。周年開花性がありますが、冬は寒さで少なくなります。インドのベンガル地方が原産地で矢筈のような形をした葉を持つことが名前の由来です。温暖な気候を好み、霜が強い地域では冬越しが難しくなります。園芸品種に白花もあります。
♡♡♡ 今日のとっておき ♡♡♡
【テーブルライト】一日の終わりに、月をそっと灯してみませんか。まるで満ち欠けする月をそのまま閉じ込めたようなテーブルライトの月球儀。やわらかな光は、目にも心にもやさしく寄り添い、日々の疲れをそっとほぐしてくれます。ムーンジャーナルを書いたあとのリラックスタイムに。夜のお供にぴったりの、とっておきのアイテムです。
彡§彡 日本の庭園と公園 §彡§
【奈良県 橿原市今井町】 高木家住宅(たかぎけじゅうたく)
中尊坊通りの東端にあります。 切妻造、本瓦葺の2階建てで、1階、2階共2列6室型の部屋となっています。主屋の西側に塀と門が設けられており、そこからみせおくの裏を通り、仏間、ざしきに上がれるようになっています。これは、武士用の玄関として用いられたそうです。2階は土間の一部を除き、全体が部屋であって、畳を敷き棹縁(さおぶち)天井を張って居室としています。当家は保存もよく、幕末期の上層町家の好例です。 また、江戸時代の生活用具や火縄銃なども展示しており、座敷に上がって見ることができます。(橿原市観光情報サイトより)

「いいね!」、お気に入り登録もよろしくお願いします 。拝
ミミミご一読ありがとうございましたミミミ
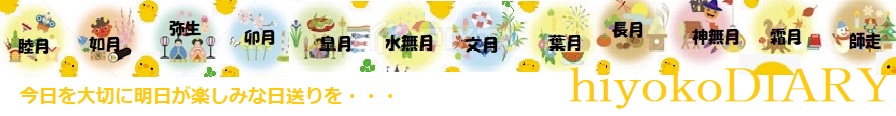

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/276bccde.19be1e66.276bccdf.aecad277/?me_id=1319109&item_id=10004260&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnihonkaki-annex%2Fcabinet%2Fimge7704792.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a9368af.520eebcf.4a9368b0.7109a9ca/?me_id=1277064&item_id=10023711&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fflaner%2Fcabinet%2Ft_img31%2Ff10023560-001.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21b8975e.2153c76b.21b8975f.db4dc099/?me_id=1213310&item_id=21432338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3780%2F9784023323780_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
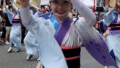

コメント頂けると励みになります。 いつも応援いただき深く感謝申し上げます。