
おはようございます。本日のお日柄は以下の通りです。
日出 5:49 / 91度
日没 17:50 / 269度
昼時 12:00
月出 20:41 / 109度
月没 6:55 / 255度
正午月齢 17.1
きのと とり :(乙酉)人気にかかわらず上がる
先勝ち : 急用や訴訟などに用いて吉の日とされています。ただし午後は凶となります。
やぶる : 破 物事を突き破る日とされています。したがって、訴訟や談判事などには吉ですが、神仏の祭祀、祝い事などはすべて凶です。
危(き) : 壁塗り、船請負、酒造り吉。登山、高所での仕事大凶。
一白 : 【天 象】冬・寒冷・雨・雪・霜・霧・霞・水害・潮の干満・月・深夜・午後十一時~午前一時(子の刻)・十二月 (子月)・北方三〇度【色・数】暗黒色 白色一・六【象 意】流水・暗黒・闇・内部・裏・かけひき 交合・親愛・胎・色情・売春・裏切り・貯智・秘密・冷静・瞑想・理性・推理・陰謀・苦悩・貧困・どん底・夜逃げ・流転・薄命・孤独・睡眠・安らぎ・永続・延長・引力・慈愛・建娠・密通・忍耐【人 物】中年男性・僧侶・仲介者・貧困者・盲人・部下・病人・売春婦・逃亡者【植 物】寒椿・寒梅・柊・藤の花・杉・槍・水仙・福寿草・水草類
神よし : 神事祭礼、宮参りに善く、不浄のことには忌む日とされています。
ぶく日 : 凶事なら凶事が重なる日。婚礼や葬式にはよくない日とされています。
彼岸入り : 春分・秋分の日の前後七日間を称し、春の彼岸は新暦三月十七日頃に入り、二十三日頃まで、秋の彼岸は新暦九月二十日頃に入り、二十六日まで、各入りから四日目が彼岸の中日(春分の日・秋分の日)です。この日祖先の霊を供養し、法会、墓参りなどが行われます。暑さ寒さも彼岸までと称されているように、暑さ寒さもようやく峠を越して温和な季候となります。
一粒万倍日 : 一粒の種が万倍に増える吉日です。そのため諸事成功を願って事始めに用いられ、とくに商売始め、開店、金銭を出すのに善いと言われています。反面、ふえて多くなる意味から人から物を借りたり、借金をするのには凶日です。
不成就日 : 障りがあって物事が成就せず、悪い結果を招く凶日とされています。とくに婚礼、開店、柱建て、命名、移転、契約事などには不向きでこの日に急に何事かを思い立ってり願い事をすることも避けるべきとされています。
東京のお天気 : 曇り
最高気温 15度 / 最低気温 8度
満潮 6:10 18:46
干潮 0:26 12:36
◇◇◇今日のひと言◇◇◇
憂鬱で気持ちも落ち込む彼岸になりました。なんでこんなに気持ちが悪いのかわかりません。どうか安らかに。
☆彡 ☆彡お花の事☆彡 ☆彡
オクナセルラタ(花言葉「心躍る」)オクナ科オクナ属
オクナの仲間は常緑性の高木から低木で、旧世界の熱帯(アフリカ、マダガスカル、マスカリン諸島、インド、東南アジア)などに約90種が分布します。タイやベトナムではオクナ・インテゲリマ(Ochna integerrima)が栽培されますが、日本ではミッキーマウスノキと呼ばれるオクナ・セルラータ(O. serrulata)が植物園の温室などで栽培されてきました。近年は鉢植えが市販されるようになり、熱帯花木として一般家庭でも栽培されるようになりました。ミッキーマウスノキは、春から夏にかけて次々に咲く、澄んだ黄色の花も観賞価値の高いものですが、なんといっても名前の由来となったユニークな形の果実が魅力です。開花後に、がくが赤くなってだんだんと盛り上がり、黒色に熟した果実がついた姿がミッキーマウスの顔に見えることがあります。熱帯花木としては寒さに比較的強いため、関東地方南部以西の暖地であれば一年中戸外でも栽培できます。冬に温度が低いと落葉することがありますが、芽が生きていれば、春に芽吹きます。長く育てていると、枝が伸び、下葉が落ちて樹形が乱れるので、定期的な剪定で樹形をコンパクトに保つようにします。
♡♡♡ 今日のとっておき ♡♡♡
【ポーランド食器】彩りがかわいい、ポーランド食器。パスタでもカレーでもパーティーでも普通ランチでも喜んでもらえそうです。
彡§彡 日本の庭園と公園 §彡§
【大阪府 牧方氏】 淵埋山 光善寺(こうぜんじ)
出口は、文明七年(1475)本願寺第八世蓮如上人が建立した御坊を中心に発達した寺内町である。寺内町は、室町時代に浄土真宗などの仏教寺院、道場(御坊)を中心に形成された自治集落をのことをいう。蓮如上人は御坊(のちに光善寺)を拠点に摂津・河内・和泉で布教活動を行い、三年後、山城に創建した山科本願寺に移った。蓮如上人の死後、光善寺は戦国乱世の中で退転を余儀なくされ、旧地に復したのは慶長年間(1596-1615)であった。広大な寺域と御堂・山門・通用門・鐘楼・太鼓楼・書院・庭園などの江戸時代の伽藍を残し、寺内町の核としての風格を今に伝えている。その景観は、「河内名所図会」(享和元年刊)にみえるものとよく一致し、江戸後期にさかのぼるものである。伽藍の近世建築には、17世紀の山門および脇門、江戸中期の数寄屋風書院があり、天明二年(1782)の御堂、同七年の太鼓楼等がある。出口は京都と大阪の中間地点で淀川の南岸に接し、水陸交通の便利な土地柄でした。 当時この地には二丁四方(一万四千四百坪)の大きな池があり、それを埋め立てて諸堂を建設されましたので、山号を淵埋山(えんまいざん)と名づけられました。 その池は今も小さく残され、石川丈山作という光善寺庭園の一部となっています。(光善寺HPより)

「いいね!」や、お気に入り登録もよろしくお願いします 。拝
彡 ω彡 ご一読ありがとうございましたω彡ω
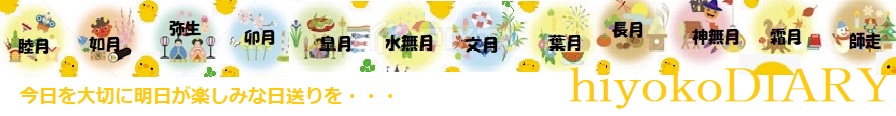

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2e60945b.30390904.2e60945c.af9f3f0b/?me_id=1373910&item_id=10000059&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbbkomada%2Fcabinet%2Fokou%2Fcompass1591668037.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/276bd23d.cbb9ef6f.276bd23e.5d1507e5/?me_id=1377486&item_id=10043934&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fengei3r%2Fcabinet%2Fm024%2F126634.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2f3cef8a.02d5f127.2f3cef8b.cd8ec13d/?me_id=1275222&item_id=10005846&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkersen%2Fcabinet%2F202005wiza%2Fw204-l15.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21b8975e.2153c76b.21b8975f.db4dc099/?me_id=1213310&item_id=20340897&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1394%2F9784046051394_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント頂けると励みになります。 いつも応援いただき深く感謝申し上げます。